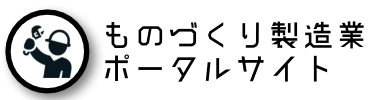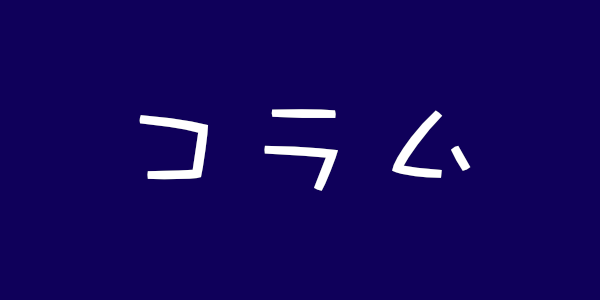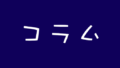製造業といえば「自由業種」と思われがちですが、実は業種によって許認可・届出・登録が必要な場合があります。特に食品、医薬品、化学品、電気機器、金属加工などは、各種法令の対象となり、知らずに営業を始めると違法状態になるリスクも。
本記事では、製造業に関連する主要な許認可制度を業種別に整理し、それぞれの手続き、所管省庁、注意点、違反時の罰則などを、できるだけ具体的かつ実務的にまとめました。
製造業における「許認可」とは何か
許認可とは、国や自治体が「事業活動を行う前提として義務付ける手続き」です。大きく以下のように分類されます:
- 許可:厳しい条件の下、行政の裁量で与えられる(例:医薬品製造)
- 認可:法令上の基準を満たせば基本的に認められる(例:計量器製造)
- 登録:必要な書類を提出して名簿に記載(例:電気用品製造)
- 届出:一定の条件のもとで届け出を行う(例:化学物質製造)
製造業では「許可+届出」が必要なケースもあり、都道府県ごとに対応が異なる点も要注意です。
主要な製造業別の許認可一覧(早見表)
| 業種 | 対象となる許認可制度 | 所管省庁 |
|---|---|---|
| 食品製造 | 食品衛生法による営業許可 | 厚生労働省 / 保健所 |
| 医薬品・化粧品製造 | 薬機法に基づく製造業許可 | 厚生労働省 / 都道府県 |
| 毒物・劇物製造 | 毒劇法に基づく製造業登録 | 厚生労働省 |
| 化学物質製造 | 化審法 / PRTR法による届出 | 環境省・経済産業省 |
| 電気機器製造 | PSE法による製造事業者登録 | 経済産業省 |
| 計量器製造 | 計量法に基づく指定製造事業者制度 | 経済産業省 |
| 鉄鋼・非鉄金属製造 | 特定施設届出(騒音・振動・ばい煙) | 都道府県・市区町村 |
| 再生資源加工 | 廃棄物処理法による処分業許可 | 環境省 / 都道府県 |
個別制度の概要と手続きフロー
1. 食品製造業(食品衛生法)
- 対象:食品・菓子・パン・飲料等の製造業
- 所管:保健所
- 手続き:営業許可申請 → 実地検査 → 許可証発行
- 期間:約30日程度
- 費用:15,000円〜40,000円程度(自治体により異なる)
2. 医薬品・化粧品製造業(薬機法)
- 対象:化粧品・医薬部外品・医薬品の製造
- 要件:品質管理責任者の配置、GMP適合設備
- 罰則:無許可営業は3年以下の懲役または300万円以下の罰金
3. 電気用品製造業(PSE法)
- 対象:コンセント接続型の電気製品
- 義務:製品ごとにPSEマークの取得
- 販売元も製造事業者としての届出が必要
4. 金属加工業に関連する環境法令
- 対象:プレス、溶接、切削、メッキ工程など
- 必要届出:特定施設届出(騒音規制法、振動規制法)
- 都道府県への事前届け出義務
許認可を受ける際の一般的な流れ
- 該当法令の調査(業種・品目に対する義務の確認)
- 所管官庁または自治体への相談
- 必要書類の準備(施設図面、管理者経歴、機器リストなど)
- 書類提出・審査・実地確認
- 許可証・登録証の交付
業種によっては許可までに2〜3ヶ月かかるケースもあり、事業開始のスケジュールに影響します。
許認可が必要な業種の見落としがちな例
- 金属研磨や切削業が「ばい煙発生施設」として届け出対象になる
- 再生プラスチック製品製造で「廃棄物処理法」の規制対象となる
- 3Dプリンタで樹脂を使う工程が「有機溶剤作業」として労安法の規制対象になる
現代的な製造工程(例:レーザー加工、ドローン部品の開発など)でも、既存法令に抵触する可能性があります。
無許可営業のリスクと罰則例
| 対象法令 | 違反行為 | 罰則 |
|---|---|---|
| 食品衛生法 | 営業許可を取らずに食品を製造販売 | 2年以下の懲役または200万円以下の罰金 |
| 薬機法 | 化粧品を無許可で製造 | 3年以下の懲役または300万円以下の罰金 |
| PSE法 | PSEマークなしの製品販売 | 1年以下の懲役または100万円以下の罰金 |
| 計量法 | 無認可で計量器製造 | 6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金 |
罰則だけでなく、「取引先との契約解除」「行政処分による営業停止」など、経営面のダメージも大きくなります。
製造業許認可取得の支援制度・相談先
- 都道府県の産業振興課・保健所:食品や環境関係
- 経済産業局:化学品・電気用品・計量器
- 中小企業診断士・行政書士:手続き代行・書類作成支援
- 補助金情報サイト(J-Net21):設備・改修支援と連動
一部業種では、許認可取得のための改修工事に対して補助金や税制優遇(例:中小企業経営強化税制)が適用される場合もあります。
よくある質問(FAQ)
Q1. 許認可なしで始められる製造業はありますか?
はい。金属部品加工、木工製品製造、家具製造、プラスチック成形など、許認可不要な業種もあります。ただし、消防法・労働安全衛生法等の一般規制は常に適用されます。
Q2. 自宅工房で食品製造は可能ですか?
原則として食品製造は「営業許可施設」の条件を満たす必要があります。一般住宅での兼用は厳しいため、専用スペースを確保する必要があります。
Q3. 許認可の更新は必要ですか?
多くの許可証は「有効期限(5年など)」が設定されており、期限前の更新手続きが必要です。変更(設備・所在地・責任者)時も再届出が求められることがあります。
まとめ:製造業の許認可は「事業戦略」の一部として扱おう
製造業を営む上で、法令上の許認可は「障壁」ではなく「事業の信頼性を高める要素」です。制度を正しく理解し、必要な対応を怠らないことが、将来的なトラブル回避や顧客・取引先からの信頼向上につながります。
- 製造業でも許認可が必要な業種は意外と多い
- 手続きは自治体や管轄官庁によって異なるため、事前相談が重要
- 法令違反には営業停止や罰則のリスクがある
これから製造業を始める方、または業種転換・新規製品開発を検討中の方は、まず一度「自社業務に必要な許認可があるか?」を棚卸ししてみましょう。適切な許認可取得は、成長の足かせではなく未来への土台となります。