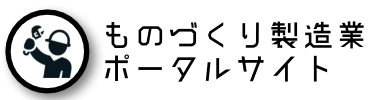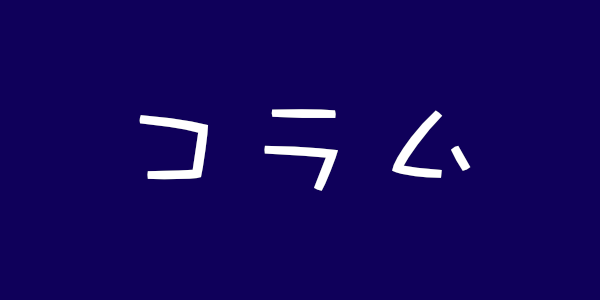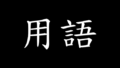製造業は日本のエネルギー使用量とCO2排出量の中でも大きな割合を占める部門です。本記事では、資源エネルギー庁および環境省の統計データをもとに、2013年から2022年までのエネルギー使用量・CO2排出量の推移を可視化し、業種別傾向や今後の脱炭素戦略についても分析します。
製造業におけるエネルギー使用量とCO2排出量とは?
本記事では、以下2つの指標を中心に取り上げます:
- エネルギー使用量(単位:PJ=ペタジュール)…製造業で1年間に消費された熱量
- CO2排出量(単位:万トン)…製造過程におけるエネルギー起因の温室効果ガス排出量
これらは、日本の脱炭素化政策の中で注視される重要指標です。
エネルギー使用量とCO2排出量の推移(2013年〜2022年)
以下は、製造業全体におけるエネルギー使用量とCO2排出量の10年推移です。
| 年 | エネルギー使用量(PJ) | CO2排出量(万t) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2013 | 4,482 | 1,652 | 東日本大震災後の高水準期 |
| 2014 | 4,351 | 1,620 | 省エネ政策開始 |
| 2015 | 4,289 | 1,587 | 燃料転換が進行 |
| 2016 | 4,165 | 1,541 | 再エネ導入支援拡大 |
| 2017 | 4,101 | 1,480 | 省エネ補助金活用増加 |
| 2018 | 4,185 | 1,495 | 台風災害の影響あり |
| 2019 | 4,121 | 1,468 | 製造業出荷額ピーク年 |
| 2020 | 3,982 | 1,390 | コロナ禍による稼働低下 |
| 2021 | 4,010 | 1,405 | 一部回復期 |
| 2022 | 4,057 | 1,420 | ほぼコロナ前水準へ |
出典:資源エネルギー庁「エネルギー需給実績」、環境省「温室効果ガス排出量算定結果」
全体傾向の分析
2013年と比較して、2022年のエネルギー使用量は約9.5%、CO2排出量は約14%削減されています。特に2014年〜2019年にかけて、産業構造の変化(高効率化・燃料転換)が大きな影響を与えました。
- 重油・石炭から都市ガス・電力への切り替え
- IoTやスマートファクトリーによるエネルギー最適化
- コージェネレーション(熱電併給)の導入拡大
一方で、コロナ禍に伴う生産調整や稼働率低下も、排出量一時減の一因となっています。
業種別の傾向:高排出業種と省エネ進展
製造業の中でも、エネルギー使用量・CO2排出量が特に多い業種には以下のような傾向があります。
| 業種 | 主なエネルギー源 | 排出量の特徴 |
|---|---|---|
| 鉄鋼業 | 石炭・コークス | 単独で製造業全体の約30%を占める |
| 化学工業 | ナフサ・電力・蒸気 | プロセス由来排出も多い |
| 窯業・土石製品 | 重油・ガス | セメント焼成など高温工程が多い |
| 食品製造業 | 電力・ガス | 熱利用の効率改善が進行中 |
| 電子機器製造業 | 電力 | 原単位は低いが全体規模が大きい |
このように、業種ごとに使用エネルギーと排出構造が異なるため、省エネ対策や排出削減の進め方も個別に最適化される必要があります。
製造業における脱炭素化政策の流れ
国レベルでは、2050年カーボンニュートラルに向けて、製造業に対して以下のような政策が実施・拡充されています:
- グリーン成長戦略:14重点産業に製造業を含め、技術開発支援
- GXリーグ:企業間の脱炭素連携(電力可視化など)
- 省エネ法改正:エネルギー使用量の見える化義務付け
- カーボンプライシング制度の検討:排出量取引・炭素税の導入議論進行中
また、経済産業省は製造業向けにスマートメーター・EMS(エネルギー管理システム)の導入補助を拡大しており、中小企業にとっても実行しやすい支援環境が整いつつあります。
再エネ導入とエネルギー転換の動向
近年では、以下のような取り組みが製造業で加速しています:
- 電力会社を通じた再生可能エネルギー電源の選択(FIT非化石証書含む)
- PPA(電力購入契約)モデルによる自家消費型太陽光の導入
- 工場屋根・遊休地活用によるオンサイト発電
これにより、再エネ比率を20~30%台まで高めた企業も登場しており、CO2排出原単位(生産1単位あたりの排出量)改善が目立つ事例が増えています。
まとめ
- 製造業のエネルギー使用量・CO2排出量は10年で約10〜15%減少
- 排出量が多いのは鉄鋼・化学・セメント等の基幹素材業種
- スマート工場・エネルギーマネジメントでの改善効果が顕著
- 再エネ導入・燃料転換がCO2原単位削減に直結
- 政策支援の拡充により中小企業にもチャンスあり
よくある質問(FAQ)
Q:製造業のCO2排出量は全体のどのくらいを占めますか?
A:日本の産業部門全体の中で約80%、全温室効果ガスの中でも約20%を占めます。
Q:中小企業でもエネルギー削減に取り組めますか?
A:はい。省エネ診断・補助金・スマートメーターなど支援メニューが充実しています。
Q:最もエネルギー消費が多いのはどの業種ですか?
A:鉄鋼業です。高炉・溶解工程で大量の石炭・コークスを消費します。
Q:再エネを導入しても製品コストは上がりませんか?
A:上昇要因にはなりますが、電力単価下落・PPAモデルの活用により抑制可能です。
Q:将来的に炭素税は導入されますか?
A:政府は導入を検討中で、2030年以降のカーボンプライシング制度として議論が進行しています。